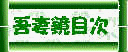
建久十年(1199)己未四月大
|
建久十年(1199)四月大一日壬戌。被建問注所於郭外。以大夫属入道善信。爲執事今日始有其沙汰。是故將軍御時。營中點一所。被召决訴論人之間。諸人群集。成皷騒。現無礼之條。頗爲狼藉之基。於他所可行此儀歟之由。内々有評議之處。熊谷与久下境相論事對决之日。直實於西侍除鬢髮之後。永被停止御所中之儀。以善信家爲其所。今又被新造別郭云々。 |
建久十年(1199)四月大一日壬戌。問注所於郭外①に建被る。
たいふさかんにゅうどうぜんしん もっ しつじたる きょう
はじ そ さた あ
大夫属入道善信
を以て、執事爲に今日始めて其の沙汰有り。
これ こしょうぐん
おんとき えいちう いっしょ てん
そろんにん
めしけっ らる のかん
是、故將軍の御時、營中の一所を點じ、訴論人を召决せ被る之間、
しょにんぐんしゅう こさい な ぶれい
あらは のじょう すこぶ ろうぜきのもといたり
諸人群集し、皷騒を成し、無礼を現す之條、頗る狼藉之基爲。
たしょ をい こ ぎ
おこな べ か のよし ないないひょうぎあ のところ くまがいと くげ さかいそうろん ことたいけつのひ
他所に於て此の儀を行う可き歟之由、内々評議有る之處、熊谷与久下と境相論の事對决之日②、
なあざね にし さむらい をい びんぱつ はら ののち
なが ごしょちうの ぎ ちょうじされ ぜんしん
いえ
もっ そ ところ な
直實
西の侍に於て鬢髮を除う之後、永く御所中之儀を停止被、善信の家を以て其の所と爲す。
いままたべっかく しんぞうさる うんぬん
今又別郭を新造被ると云々。
参考①郭外は、幕府の外で、問注所を幕府内から移転した。
参考②對决之日は、12巻建久3年11月25日条で境相論して、頭にきた熊谷次郎直實は髷を落とし京へ向かう。
現代語建久十年(1199)四月大一日壬戌。裁判を担当する問注所を幕府の敷地外に建てられます。大夫属入道三善善信を筆頭の執事に、今日始めて指示がありました。これは、亡くなった先の将軍の時代に、幕府内の一箇所を指定して、原告の訴人、被告の論人を呼び出して対決をさせていましたが、関係者の人々が群れ集って騒がしいし、無礼を働くし、良くない騒ぎの基になる。こういうことは他所でやるべきじゃないかと、内内で議論が重ねられてきましたが、熊谷次郎直實と久下權守直光が対決をした時に、直實は旨く弁解が出来ないのを悔しんで、西の侍所で髷を切った事があってから、御所での実施を止めて、三善善信の家を仮にその場所としてきました。今度は、別に建物を新造するんだとさ。
|
建久十年(1199)四月大十二日癸酉。諸訴論事。羽林直令决断給之條。可令停止之。於向後大少事。北條殿。同四郎主。并兵庫頭廣元朝臣。大夫属入道善信。掃部頭親能〔在京〕。三浦介義澄。八田右衛門尉知家。和田左衛門尉義盛。比企右衛門尉能員。藤九郎入道蓮西。足立左衛門尉遠元。梶原平三景時。民部大夫行政等加談合。可令計成敗。其外之輩無左右不可執申訴訟事之旨被定之云々。 |
読下し しょ そろん こと うりん
じき けつだんせし たま のじょう これ
ちょうじせし
べ
建久十年(1199)四月大十二日癸酉。諸訴論の事、羽林直に决断令め給ふ之條、之を停止令む可し。
きょうこう だいしょう こと をい ほうじょうどの おな しろうぬし なら ひょうごのかみひろもとあそん たいふさかんにゅうどうぜんしん
向後は大少の事に於て、北條殿、同じき四郎主、并びに兵庫頭廣元朝臣、 大夫属入道善信、
かもんのかみちかよし 〔ざいきょう 〕 みうらのすけよしずみ はったのうえもんのじょうともいえ わだのさえもんのじょうよしもり ひきのうえもんのじょうよしかず
掃部頭親能〔在京す〕、
三浦介義澄、 八田右衛門尉知家、和田左衛門尉義盛、比企右衛門尉能員、
とうくろうにゅうどうれんさい あだちのさえもんのじょうとおもと かじわらのへいざかげとき みんぶたいふゆきまさら
だんごう くは
藤九郎入道蓮西、
足立左衛門尉遠元、 梶原平三景時、
民部大夫行政等談合を加へ、
はか
せし せいばいすべ そ ほかのやから そう
な そしょう こと と もう べからずのむね
これ さだ らる うんぬん
計ら令め成敗可し。其の外之輩は左右無く訴訟の事を執り申す不可之旨、之を定め被ると云々。
現代語建久十年(1199)四月大十二日癸酉。諸人の訴訟ごとを頼家様が直接判断をすることは、止めにしましょう。今後は、全ての訴訟を北条時政殿・同四郎義時主・兵庫頭広元さん・大夫属入道三善善信・掃部頭中原親能〔京都に居ます〕・三浦介義澄・八田右衛門尉知家・和田左衛門尉義盛・比企右衛門尉能員・藤九郎蓮西(安達盛長)・足立左衛門尉遠元・梶原平三景時・民部大夫行政(二階堂)達が会議をした上で判断を下すようにしましょう。その他の者達が安易に訴訟問題を扱うべきではないと、決めたんだとさ。
説明直に决断令め給ふ之條。之を停止令む可しは、有名な「將軍直接判断権」を取り上げ、
北条時政 ・北条義時
・北条義時 ・大江広元
・大江広元 ・三善康信
・三善康信 ・中原親能
・中原親能
三浦義澄 ・八田知家
・八田知家 ・和田義盛
・和田義盛 ・比企能員
・比企能員 ・安達盛長
・安達盛長
足立遠元 ・梶原景時
・梶原景時 二階堂行政
二階堂行政 の十三人合議制
の十三人合議制![]() にした。最近は、研究が進み将軍頼家決裁への上申前の検討との意見もある。
にした。最近は、研究が進み将軍頼家決裁への上申前の検討との意見もある。
|
建久十年(1199)四月大廿日辛巳。爲梶原平三景時。右京進仲業等奉行。書下政所云。小笠原弥太郎。比企三郎。同弥四郎。中野五郎等從類者。於鎌倉中。縱雖致狼藉。甲乙人敢不可令敵對。若於有違犯聞之輩者。爲罪科。慥可尋注進交名之旨。可觸廻村里之由。且彼五人之外。非別仰者。諸人輙不可參昇御前之由云々。 |
読下し かじわらのへいざかげとき うきょうのしんあかなりら
ぶぎょう な まんどころ か くだ い
建久十年(1199)四月大廿日辛巳。梶原平三景時、 右京進仲業等奉行と爲し、政所に書き下して云はく①、
おがさわらのいやたろう ひきのさぶろう どういやたろう なかののごろうら じゅうるいは かまくらちう をい たと ろうぜき
いた いへど
小笠原弥太郎、比企三郎、同弥四郎、中野五郎等の從類者、鎌倉中に於て、縱い狼藉を致すと雖も、
とこうのひと あえ
てきたいせし べからず
甲乙人②敢て敵對令む不可。
も いはん きこ あ のやから をい は
ざいか な たしか きょうみょう たず
ちうしんすべ
のむね そんり ふ めぐ べ のよし
若し違犯の聞へ有る之輩に於て者、罪科と爲し、慥に交名を尋ね注進可し之旨、村里に觸れ廻らす可し之由、
かつう か ごにんのほか べつ
おお もの あらず
しょにんすなは ごぜん まい
のぼ べからずのよし うんぬん
且は彼の五人之外、別に仰せる者に非ば、諸人輙ち御前に參り昇る不可之由と云々。
参考①政所に書下して云はくは、書いて張り出したので「壁書」と云う。
参考②甲乙人は、とこうのひと、とやかく言う人から来てる。ここでは庶民。
現代語建久十年(1199)四月大二十日辛巳。梶原平三景時と右京進仲業が指揮担当して、政務執事場所の政所に張り紙をして云いました。小笠原弥太郎長経、比企三郎、同弥四郎時員、中野五郎能成達の将軍取巻き連中が、鎌倉の中では、たとえ無茶な振る舞いをしたとしても、庶民は歯向かってはいけない。若し云う事に反していると耳に入った者は、罪人として名前を調べて書き出すように、村や里へお触れを出すように、しかも、その五人以外のものは、又特別な仰せがなければ、簡単に将軍にお会いさせないと決めたんだとさ。
|
建久十年(1199)四月大廿三日甲申。故將軍百ケ日御忌辰也。於御持佛堂。被修佛事。佛。新圖釋迦阿弥陀各一鋪。經。法華經六部。導師莊嚴房阿闍梨行勇云々。 |
読下し こしょうぐんひゃっかにち ごきしん なり おんじぶつどう をい ぶつじ しゅうさる
建久十年(1199)四月大廿三日甲申。故將軍百ケ日の御忌辰也。御持佛堂に於て、佛事を修被る。
ほとけ しんず
しゃか あみだ おのおの いちほ きょう
ほけきょうろくぶ どうし
しょうごんぼうあじゃりぎょうゆう うんぬん
佛は、新圖の釋迦阿弥陀 各 一鋪。經は、法華經六部。導師は莊嚴房阿闍梨行勇と云々。
現代語建久十年(1199)四月大二十三日甲申。亡き頼朝様の百か日の法事の日です。御所裏山の持仏堂で、法事の儀式を行いました。飾った仏様は、新しく描いたお釈迦様と阿弥陀様の絵が一幅づつです。あげたお経は、法華経六巻です。指導僧は、荘厳坊阿闍梨退耕行勇なんだとさ。
説明莊嚴房阿闍梨行勇は、退耕行勇1163-1241。相模の人。先に真言密教を学び、栄西について臨済禪を修め寿福寺二世。初出演。
| 正治元年(1199)四月大廿七日戊子。仰東國分地頭等。可新開水便荒野之旨。今日有其沙汰。凡稱荒不作等。於乃貢減少之地者。向後不可許領掌之由。同被定云々。廣元奉行之云々。 |
読下し
とうごくぶん ぢとうら おお すいびん
こうや しんかいすべ のむね きょう そ
さた あ
正治元年(1199)四月大廿七日戊子。東國分地頭等に仰せて、水便の荒野を新開可き之旨、今日其の沙汰有り。
およ あれふさくなど しょう のうぐげんしょうのち をい は きょうこうりょうしょう ゆる べからずのよし
おな さだ
らる うんぬん
凡そ荒不作等と稱し、乃貢減少之地に於て者、向後領掌を許す不可之由、同じく定め被ると云々。
ひろもとこれ ぶぎょう
うんぬん
廣元之を奉行すと云々。
現代語正治元年(1199)四月大二十七日戊子。関東など東国の地頭達に言いつけて、水の便のある荒野を新しく開拓しなさいと、今日その命令を出されました。だいたい、荒れてしまったとか、不作なんだと言って、年貢が減ってきている土地については、今後領地として預けておく事はないと、同様に決められましたとさ。大江広元がこれを指示担当しましたとさ。
説明関東地方の新開発は、政所行政が成立したから新しい政策を進めることが出来る。