
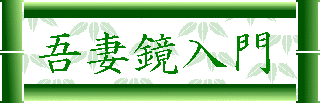
このバナーをクリックして目次へお入りください
鎌倉歴史散策の歴散加藤塾別館 吾妻鏡入門の頁です。
今日は、令和6年甲辰5月1日(水)旧暦の三月廿三・乙丑・五黄・先勝
このサイトは、歴散加藤塾が「吾妻鏡」を下記の資料を基に、@塾長なりに研究解釈しています。
参考図書:*吉川弘文館『国史大系吾妻鏡』黒板勝美著 *東洋堂刊行『吾妻鏡標註』堀田璋左右著文訳
*新人物往来社『全譯吾妻鏡』貴志正造訳注 *岩波文庫『吾妻鏡』龍粛訳註 *『校訂増補吾妻鏡』廣谷國書「吉川本」
参考:原文は年初めに「治承四年庚子」とあり、月の初めに「八月小」と書かれ、日の条には「十七日丁酉」などとしか書かれていない。
しかし、各文章を引用する時に分かり易くするため、便宜上各日ごとに「治承四年(1180)八月小十七日丁酉」と「年月日」を頭に振った。
参考:文末に「云々」の語があるが、東大系は「うんぬん」と読み、京大系では「しかじか」と読むそうな。
意味は、「と言われている」とか「と伝えられている」のようだが、あえて「だとさ」とか「○○だそうな」と楽しんでいる。
なお「輩」は現在「やから」と読むが、当時は「ともがら」と読むのが正しいようだ。読み直して欲しい。
更新状況
原文の漢文:平成18年1月1日更新 52巻全て記録済み。時々入力ミスを直してます。
かなふり読下し:平成27年1月22日更新:52巻・文永3年(1266)まで完了。時々間違いを直しています。
現代語訳:令和元年10月17日更新:52巻・文永三年(1266)六月末までほぼ完了、旧漢字や変な表現を直しています。
丁最近の修正11巻建久二年(1191)八月大一日条の大庭平太景能の保元の乱における鎮西八郎為朝との対応の記述を直した2023.06.08
最近の修正34巻仁治二年(1241)十二月二十七日条の解説に下馬橋附近の変遷の仮説を設定してみた。2023.05.23
最近の訂正10巻建久元年(1190)十一月大九日の「不追前」を「前追せ不」に訂正し解説を付け加えた。2023.1.10
訂正10巻建久元年(1190)八月小十六日条の「的矢の種類」を阿部猛著「鎌倉武士の世界」から追加した。2021.1.14
訂正34巻欠の仁治三年(1242)3月3日付け泰時の手紙(勝長寿院の僧兵の武器の携帯禁止令)を載せる。2019.10.11
三浦三崎ひとめぐりさんの東鑑読下し![]() 参考に他の古文書の記入もあります
参考に他の古文書の記入もあります
 参考解説文一覧五十音順12巻建久3年(1192)6月末日まで整理済み2022.02.22
参考解説文一覧五十音順12巻建久3年(1192)6月末日まで整理済み2022.02.22
 40巻建長2年(1250)11月末日まで整理済み。2024.3.2
40巻建長2年(1250)11月末日まで整理済み。2024.3.2
現代語の「ブログ吾妻鏡現代語」 今 ! 神奈川宿が面白い 知っておきたい昔の法則
お客様の女子高生が書いた論文が玉川学園のHPに掲載されました。読んでみてください。
鎌倉幕府の置いた三機構についての考察
吾妻鏡研究の第一人者 奥富敬之先生が2008年7月7日逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
鎌倉古道番外編 歴史古街道団コラボ塾長と上の道を町田から鎌倉まで歩きたい
大鏡による帝王・源氏系図 系図藤性關東武士 めちゃ大所帯の藤原氏
このサイトで使用している文章も画像も引用は管理人の許可を必要とします。This site is Japanese only.